【回答】これまで使われてきた検査指針(1), (2) や他の参考書 (3), (4) には「結核菌の典型的集落は, 2〜3週以後に認められる。培養8週間を経過しても集落の発生が認められない場合は, 培養陰性として観察を打ち切ってよい」と記載されています。培養期間の設定根拠については, 確かな論文やデータが存在しないことから, お示しすることができませんが, 弊社で得ました成績を参考に質問にお答えします。
図1は, 3%小川培地と2%小川培地の培養陽性に至る日数の比較成績を示したものです。両培地とも2〜4週間で分離される件数が多いことがわかります(92〜96%検出)。つまりこれらが“典型的な集落”に値するものであり, 未治療や初期治療中の患者から分離した結核菌の多くはほぼ同じ培養日数で分離されます。4週間で分離できなかった残りの検体ですが, 特に3%小川培地では4〜8週間の培養でようやく分離される菌株が観察されています。さらに一部 (2例) は8週以降にようやく観察される検体でした。おそらく“培養8週間”はこのような成績が基となり定義されたものと推測します。また補足として, これまでの検査指針や参考書では「培養8週間を経過しても集落が認められない場合はさらに4週間くらい培養を延長する必要がある」と記載されています。ちなみに培養を延長することで, 塗沫陽性・培養陰性の検体の内, 10%強に結核菌の集落を見るとの報告もあるそうです。培養期間の設定については, 菌側はもとより, 近年新たに採用されはじめた前処理法や液体培地, さらに改良された小川培地なども影響することから, 再度設定する必要があるのではないかと考えます。
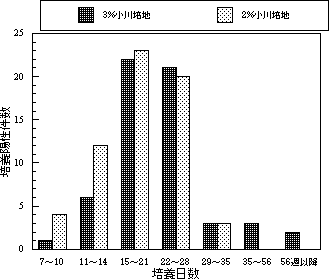
(1) 室橋豊穂, 他: 結核菌検査指針 (厚生省監修), 日本公衆衛生協会, 1992,
p20〜21.
(2) 室橋豊穂, 他: 結核菌検査指針 (厚生省監修), 日本公衆衛生協会, 1979,
p28〜29.
(3) 工藤裕是, 他: 結核菌. 微生物検査必携 細菌・真菌検査第3版 (厚生省監修),
日本公衆衛生協会, 1987, p 101〜102.
(4) 工藤裕是: 結核菌検査. 結核管理技術シリーズ1 改訂新版, 結核予防会,
1987, p 45〜46.