私は, 食品会社の試験室に勤務しているものですが, 耐熱性の胞子についてご質問があります。
われわれの試験では, 大体は85℃, 10分間のヒートショックを与えた後, 所定の培地で, 平板混釈法にて検査を行っております。この操作の後, 平板に確認されたものを耐熱性菌陽性としておりますが, 顕微鏡観察まではしておりません。グラム染色でも, 胞子の確認は出来ると聞きましたが, どのように観察されるのか, もしも映像として何かあれば, ぜひ見せていただきたいと思います。本来は, 有胞子菌を購入し, 自分で染色するべきなのですが, 食品会社ゆえ, ラボコンタミが心配で出来ません。ご協力を, よろしくお願いします。
【回答】
細菌学におけるspore (芽胞) は細胞内部に形成する内生胞子 (endospore)
に限定し, Nocardia属菌にみられるfragmentation sporeを含めないことが提唱されました
(Cross, 1970年)。故に, 通常呼称する芽胞は比較的少数の細菌に認められ, 動物の病原性菌の中ではBacillus属
(Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus stearotheromophilusなど)
とClostridium属 (Clostridium botulinum, Clostridium difficile,
Clostridium perfringens, Clostridium tetaniなど) のみであります。芽胞は比較的易熱性のものから耐熱性のものまでみられ,
生息環境条件によっても異なります。
顕微鏡による芽胞の確認には, 特殊染色法 (Moeller法やSchaeffer & Fulton法) が紹介されておりますが, 若い芽胞は脱色されやすく, 二次染色で染まったり, 染まらなかったりします。また古い培養菌では芽胞が菌体から離脱していることもあります。さらに特定の環境では, 芽胞形成性を失う場合もあり, これは一時的な場合から永久的な場合まで様々です。一時的な場合は, 培地や培養条件を変えてやれば復元することから, ジャガイモ斜面などデンプン含有培地で継代することによりBacillus属菌が復元するといわれています。芽胞の復元に最も適した培地としては土浸出液寒天 (Gordon & Smith, 1953年) があり, National Collection of Type Cultures(NCTC)保存のBacillus無芽胞菌株の多くを有芽胞状態にもどした実績が報告されています。このようなことから, 培養菌の芽胞をグラム染色鏡検で確認することはやや困難であり, 多くの場合はグラム陽性の太い桿菌として観察されるのみです。ただし, 菌種, 培養条件によっては比較的明瞭に観察される場合もあり, 菌体の端や中央など, 芽胞の存在部分が抜けて (透明または薄いピンク_青色) 見えます。また, 染色の代わりに位相差顕微鏡を用いる場合もあります。
ご希望どおりとはいきませんが, 下に3株の純培養菌のグラム染色像を示しました。Bacillus anthracisとClostridium difficileは菌体がグラム陽性色 (青色_黒紫色) に染まり, 芽胞部分は染色され難いことから薄いピンク_薄い青色として観察され, またClostridium tetaniの芽胞は, 細長い菌体の先端から太く丸い太鼓のバチ状として観察されました。参考になれば幸いです。

(Bacillus anthracis)
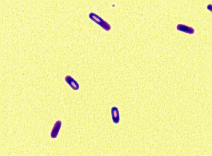
(Clostridium difficile)

(Clostridium tetani)