初めまして。臨床検査技師です。まだ細菌検査や臨床検査技師としての経験も二年と浅く, 日々勉強の毎日です。最近, 仕事が終わると充実感に身を包まれていますし, 細菌検査が楽しくなってきました。私の病院はデイドベーリングの“ウォーカウェー”を使ってます。先日, 結果報告書のコメントの欄に「CLDM誘導耐性に注意」と書かれていました。この“CLDM誘導耐性”とはどういうことなのでしょうか。少々恥ずかしい質問ですが, ご教授お願いできませんでしょうか。よろしくお願い致します。
【回答】
WalkAway の情報を管理している Data Management System (DMS) の初期設定には,
このようなコメントを付加する機能はありませんので, おそらくDMSに接続した検査システムなどにおいて,
このようなコメントが付加されるよう, 施設独自に設定されているのかと推測します。
「クリンダマイシン (CLDM) 誘導耐性」ですが, これは2004年版のNCCLS M100-S14において新たに追加されたコメントを受けてのことと思われます。以下に, NCCLSの該当箇所を引用し, その概略を示します。
NCCLS M100_S14 Table 2Cのコメント(25)には, マクロライド耐性Staphylococcus spp. のCLDM耐性に関する記載が追加されました。このコメントには, マクロライド耐性Staphylococcus spp.のなかにはCLDMにも耐性を示す菌株があることが記載されており, ディスクを利用して誘導型のCLDM耐性を検出する方法が提示されています。検出方法は, 血液寒天培地に被検菌を塗布し, CLDMディスク(2μg含有)とエリスロマイシン (EM) ディスク(15μg含有)を15 mmほど間隔をあけて置きます。培養した後, EMディスクに面する側のCLDMディスクの阻止円が平坦化した場合は, 誘導型のCLDM耐性であると判定します。CLDM耐性であった時, 生じた阻止円の形状がアルファベットの“D”の字に似ていることから“Dテスト”とも呼ばれています。
〔参考文献〕
Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Fourteenth
Informational Supplement, M100-S14. National Committee for Clinical Laboratory
Standards, Wayne, PA. 2004.
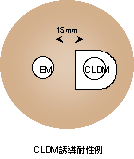 (デイドベーリング・朝倉奈津子)
(デイドベーリング・朝倉奈津子)