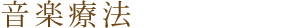音楽は、言葉にならない感情や言葉になる以前の感覚を表現することを可能にしてくれる素材です。当科で取り入れている「音楽療法」では、そんな音楽の特性を生かして、病気と向き合い乗り越える時間というよりも、一人ひとりに潜んでいる健康性を見つけ出し、自分の可能性と出会うことを大切に様々な音楽活動を行っています。
音楽は、言葉にならない感情や言葉になる以前の感覚を表現することを可能にしてくれる素材です。当科で取り入れている「音楽療法」では、そんな音楽の特性を生かして、病気と向き合い乗り越える時間というよりも、一人ひとりに潜んでいる健康性を見つけ出し、自分の可能性と出会うことを大切に様々な音楽活動を行っています。
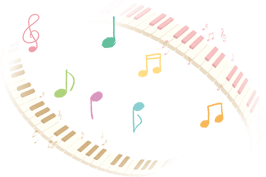 《病棟》での音楽療法は、「音楽タイム」と呼ばれる時間で、臨床心理士・音楽療法士・看護師が中心スタッフとなり、各主治医との連携の元、毎週水曜日50分間、午前は歌唱中心、午後は器楽演奏中心のセッションをデイルームで実施しています。それぞれの方のニーズやその日の調子に合わせて、お好きなプログラムに参加できます。
《病棟》での音楽療法は、「音楽タイム」と呼ばれる時間で、臨床心理士・音楽療法士・看護師が中心スタッフとなり、各主治医との連携の元、毎週水曜日50分間、午前は歌唱中心、午後は器楽演奏中心のセッションをデイルームで実施しています。それぞれの方のニーズやその日の調子に合わせて、お好きなプログラムに参加できます。
午前セッションの活動プログラムは、歌唱が中心です。ブリージング(腹式呼吸)やストレッチ等を行って、今ここにある気持ちがいい身体をしっかり作ってから歌い始めます。選曲は、参加の皆さんからのリクエスト曲が中心です。歌いたい曲を選ぶこと・その曲をみんなと歌うことなどを通して、小さな社会参加や「何かできそう…いい感じ・案外、上手くいった」というインスタントサクセス体験がもたらされます。
午後のセッションでは即興的な打楽器奏・トーンチャイムというハンドベルと似た楽器を使った和音奏・ボタン押しをしつつ弦を奏でるとコード演奏ができるオートハープの弾き歌い(お好きな曲を選曲して)などを行っています。それぞれの持ち味のテンポを崩さないようにしつつ、自由な表現(即興演奏)と役割を持った表現(コード演奏)を織込んだ場面となります。この活動では、多面的に注意を用いる認知リハビリ的な要素と、小さな挑戦からの自己効力感の向上も目指しています。
 《外来》では個人セッションとして、オーダーメイドで時間・頻度・プログラムを組み立てています。しゃっくりが止まらなくなるHic cough syndrome の患者さんへの呼吸法を中心としたセッションでの症状の消失、パーキンソン症状を持つ方へのリズム打ち歌唱による歩行改善、慢性疼痛への受容的音楽療法による疼痛緩和、脳外傷の後遺症の方への身体感覚の改善と認知機能の回復への補完効果など、用いる音楽活動は様々になります。
《外来》では個人セッションとして、オーダーメイドで時間・頻度・プログラムを組み立てています。しゃっくりが止まらなくなるHic cough syndrome の患者さんへの呼吸法を中心としたセッションでの症状の消失、パーキンソン症状を持つ方へのリズム打ち歌唱による歩行改善、慢性疼痛への受容的音楽療法による疼痛緩和、脳外傷の後遺症の方への身体感覚の改善と認知機能の回復への補完効果など、用いる音楽活動は様々になります。
音楽療法は病気の治癒に直接働きかけるものではありませんが、病気との闘いを孤独にさせないツールとして働きます。音楽的な関わりの中で自己決定をする瞬間が紡がれ、自分らしさの感覚が立ち上がっていきます。また、審美的な瞬間を提供する側面を持っているので、美的満足感も得られます。
その人がその人らしく生きることへの体温のある支援の一つとして、音楽療法は位置づけられるのではないかと考えています。