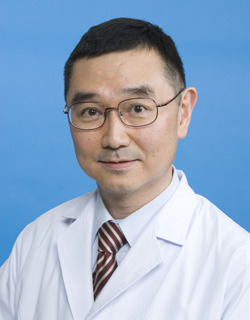 人が体の不調を訴えるとき、身体の問題だけにとどまらず、その人をとりまく心理状況や社会背景からも影響を受けています。George Engelは1977年に「生物-心理-社会モデル」を提唱し、疾病を診断し治療を適応する「生物医学モデル」だけではなく、心理、社会的要因を含めたシステムの異常として病気をとらえる必要があると述べています。すなわち、診断された疾病に注意を注ぎながらも、同時に患者の人間としての側面や、患者-医師関係、家族、社会背景といった側面にも目を向けて、これらの因子がどのように結び付いているか統合的に理解することが強調されています。
人が体の不調を訴えるとき、身体の問題だけにとどまらず、その人をとりまく心理状況や社会背景からも影響を受けています。George Engelは1977年に「生物-心理-社会モデル」を提唱し、疾病を診断し治療を適応する「生物医学モデル」だけではなく、心理、社会的要因を含めたシステムの異常として病気をとらえる必要があると述べています。すなわち、診断された疾病に注意を注ぎながらも、同時に患者の人間としての側面や、患者-医師関係、家族、社会背景といった側面にも目を向けて、これらの因子がどのように結び付いているか統合的に理解することが強調されています。これまでの精神医学では、重篤な精神病症状や慢性精神病状態の治療に重きが置かれてきました。これらも精神医学の重要な使命でありますが、近年は、より日常的なこころの健康の大切さに社会の注目が集まるようになり、青少年のいじめやひきこもり、働く人々のうつ状態や自殺問題、地域社会における老人問題、がん患者や家族の心のケアなど、新たな領域における要請が高まっています。この要請にこたえるためには、精神医療の守備範囲を精神疾患の治療のみでなく、より広汎な領域における心の医療へと拡大すべきであると考えます。
その具体的な方法としては ①こころの健康をむしばむ病態に対する早期介入医療により、治療医学にくわえ予防医学の視点をもった医療を展開し、人材を育成する。 ②コンサルテーション・リエゾン医療を通して、患者や家族の精神的健康にも配慮できるように医療従事者のスキルアップをはかり、医療現場のレベルアップに努める。 ③北陸がんプロフェッショナル養成プランや緩和医療などを通じ、がん医療にかかわる精神医学(精神腫瘍学)の普及をはかる。 ④精神科領域だけでなく、患者や家族のこころに配慮でき、患者中心の医療をおこなえる医師の育成や、チーム医療のメンバーとなるコメディカルの育成にも努める。以上の4項目をあげたいと思います。
私は金沢医科大学で学ぶ間に、先輩方から「名医となるよりも良医となれ」と教えられ、臨床家となった後もその実践に努力してきました。そして、患者自身の観点から病むことを理解すること、病むことの体験を全人的に理解することなどを通じて「患者中心の医療」を実現することが、現代医療のあるべき姿と確信するに至りました。教育者として母校に戻りました今後は、患者の満足度のみならず医療従事者の自己効力感も高める「生物-心理-社会モデル」に基づいた「患者中心の医療」を広めたいと思います。このことはまさに、金沢医科大学の建学の精神である「知識と技術をきわめ」「社会に貢献する」「良医を育てる」ことの実践にほかなりません。
